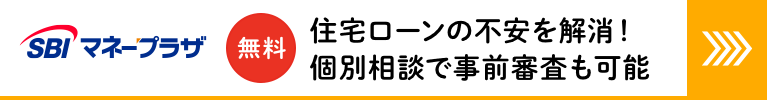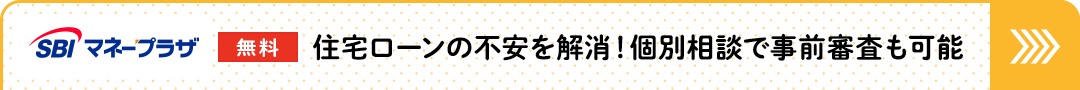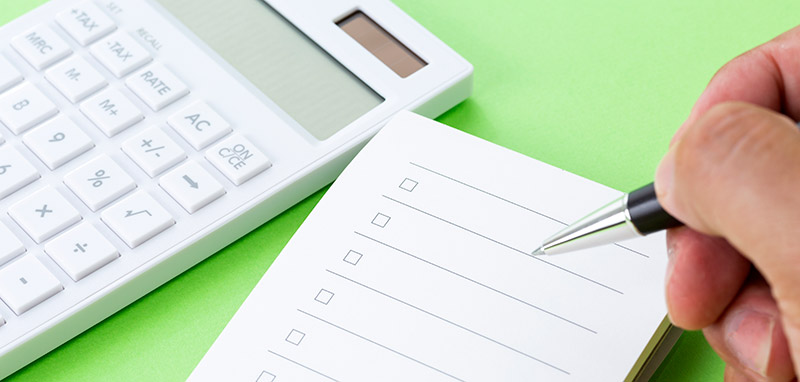
住宅ローンの借換えの際は、たんに金利やサービスを比較するだけではなく、借換えにかかる手数料を支払っても、メリットがあるかどうかを確認することが大切です。
この記事では、手数料やそれ以外にも借換時にどのような費用がかかるのか、費用の計算方法から注意点、用意できない場合について解説します。
>>あわせて読みたい(住宅ローンの借換えを判断する条件とは? 借換えのメリットと注意点)
まずは、一般的な住宅ローンの借換えには、どのような手数料(諸費用)がかかるか確認しましょう。
融資手数料は、住宅ローンを契約する金融機関に支払う、融資に伴う事務手続きなどの手数料です。金融機関によっては、事務手数料や事務取扱手数料と呼ぶこともあります。また、融資手数料の支払方法には定額型と定率型の2種類があります。
| 定額型 | 借入金額に関わらず一定額を支払う方法で、目安は2万円から30万円程度です。金額は金融機関や商品によって異なります。 |
|---|---|
| 定率型 | 借入金額に対する一定割合を支払う方法で、目安は1.0%から2.0%程度です。割合は金融機関や商品によって異なります。 |
>>あわせて読みたい(融資手数料型の住宅ローンのメリット・デメリット│保証料型との違い)
保証料は、住宅ローン契約者が融資を受けるにあたり、債務の保証を受けるために保証会社に支払う費用です。何かしらの理由で債務者が住宅ローンを返済できなくなったときに、保証契約に基づき保証会社は債務者に代わって返済を肩代わりします。その結果、債務の返済先が金融機関から保証会社に変更されますが、債務者の返済義務がなくなるわけではありません。
保証料の支払い方法には、次の2種類があります。
| 外枠方式 | 住宅ローンの契約時に一括で支払う方法です。(利用中の住宅ローンがこの方式なら、借換時に返金される場合があります。) |
|---|---|
| 内枠方式 | 住宅ローンの金利に上乗せして、毎月返済額に含めて支払う方法です。 |
金融機関や商品によっては、保証料が不要な場合がありますが、その場合は貸倒れのリスクを金融機関が負うことになりますので、その他の条件が厳しくなる可能性があります。
>>あわせて読みたい(「住宅ローンの保証料とは?」支払方法の種類とメリット・デメリット)
印紙税は、金融機関と住宅ローンの契約書を取り交わす際に課税される税金です。印紙税は借入額に応じた金額の収入印紙を購入して、契約書に貼付して割印することで納税します。
【印紙税の税額の一例】
| 借入金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,0000万円超~5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 6万円 |
(2024年4月時点)
期限前完済手数料は、借換えにともなって利用中の住宅ローンを完済するために必要な手数料で、返済先の金融機関に対して支払います。
手数料の金額は、金融機関や住宅ローン商品によって異なり、また同じ金融機関でも窓口かインターネットかなど、手続きするチャネルによっても異なる場合があります。目安としては、無料から数万円程度と考えておくと良いでしょう。
借換えにともなって、住宅ローンの担保として物件に設定されている抵当権を変更する必要があります。利用中の金融機関の抵当権を抹消し、新たに借入先の金融機関の抵当権を設定するために、それぞれ手続きで費用が必要となります。
| 抵当権抹消登記の登録免許税 | 不動産1個につき1,000円 |
|---|---|
| 抵当権設定登記の登録免許税 | 借入額の0.4% (「住宅家屋証明書」が発行され軽減税率の特例を受けた場合) |
(2024年4月時点)
抵当権の抹消登記や設定登記の申請手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士報酬が必要になります。司法書士報酬の目安は数万円~十数万円ですが、対象の住宅や借入額、司法書士によっても異なります。
借換えにあわせて、契約中の火災保険を解約することとなった際など、新たに火災保険に加入し直す場合は、火災保険料が必要となります。
長期契約の火災保険を途中解約する場合、未経過分の火災保険料が返金されますので、新たに加入する火災保険料にあてることもできるでしょう。
ここまで借換えにかかる手数料について解説しましたが、ここでは、それぞれの費用が借換え手続きのどの段階で必要となるか確認してみましょう。
借換えのための手数料を支払うタイミングについて、一般的な借換え手続きの段階に沿って見ていきましょう。金融機関や商品によって異なるので、必ずご自身でもご確認ください。
| 借換手続きの段階 | 諸費用の項目 |
|---|---|
| ① 借換えの申込み・審査・承認 | なし |
| ② 利用中の住宅ローンの一括完済の申込み | なし |
| ③ 借換えの契約手続き | ・印紙税 ・抵当権抹消・設定費用 ・司法書士への報酬 |
| ④ 融資実行・一括完済 | ・融資手数料 ・保証料(外枠方式の場合) ・期限前完済手数料(繰上返済完済手数料) ・火災保険料(加入し直す場合) |
| ⑤ 返済中 | ・保証料(内枠方式の場合) ・火災保険料(更新がある場合) |
それぞれの手数料について、いつ・いくら必要なのか確認し、準備できるようにしましょう。もし、手数料を準備することが難しい場合は、次で説明する手数料を借入金額に含めることのできる住宅ローンも選択肢となります。
金融機関や商品によっては、借換えのための諸費用を借入金額に含めることができます。こちらは住宅ローンの借換手数料が用意できない場合は?で詳しく説明しておりますのでご覧ください。
>>あわせて読みたい(住宅ローン借換えの流れ|メリット・デメリットから注意点まで)
続いて、住宅ローンの借換えにかかる手数料について、注意点を見ていきましょう。
前章の通り、借換えにかかる手数料は借入金額に含められる場合があります。ただし、これによって借換えによる利息軽減効果が失われないか、確認する必要があります。せっかく利用中の住宅ローンよりも低金利で借換えることができても、手数料を含め借入金額が増えることで、かえって負担が大きくなると本末転倒です。あらかじめご自身でシミュレーションするか、金融機関などに相談して確かめておきましょう。
>>あわせて読みたい(住宅ローンの借換時に固定金利か変動金利かを選ぶポイント)
現在利用している住宅ローンの保証料を外枠方式で支払っている場合、借換えによって当初の返済期間前に繰り上げ完済しますので、未経過分の保証料が返金されることがあります。一般的には、保証料から期限前完済手数料が差し引かれ返金されます。
なお、保証料を住宅ローンの金利に上乗せして支払う内枠方式の場合は、未経過分の保証料を支払っていませんので返金はありません。
返済中の債務者の死亡などのリスクに備える団体信用生命保険(以下、「団信」)の保険料は、通常、住宅ローンの金利に含まれています。そのため、団信の保険料は、借換時に必要な手数料ではありません。
団信(特約)の内容は、金融機関によっても異なりますので、借換時にご自身に合った保障内容の団信に見直しすることも大切です。ただし、借換時の健康状態によって団信加入の可否が決まりますので、健康状態によっては団信の見直しができないだけでなく、借換え自体もできなくなる可能性がある点には注意が必要です。
住宅ローンの借換えには様々な諸費用がかかることを説明してきました。これらはすべて合わせると、借入れる額によって数十万円から百万円以上かかることもあり、借換えたいタイミングで用意するのが難しい場合もあるかもしれません。これらを用意できない場合にはどういった方法が考えられるのでしょうか。
●諸費用を住宅ローンに組み込む
多くの商品では、借換えにかかる諸費用を、借換先の住宅ローンに組み込むことが可能です。ただし、諸費用の分借入金額が多くなり、金利負担や返済額も多くなるので、諸費用込で借り換えたときにも元の住宅ローンと比べてメリットが出るのか改めてシミュレーションを行い確認してみましょう。
なお、手数料をローンに組み込めるか否か、また、どこまでの手数料なら組み込めるかは金融機関によって異なるのでご注意ください。
●手数料の安い金融機関を選ぶ
借換えにかかる手数料を準備することが難しい場合は、少しでも手数料が安い金融機関を選ぶことも大切です。借換えにはさまざまな手数料がかかりますが、特に事務手数料と保証料は金融機関により大きな差があります。
また、事務手数料を定率型にするのか、定額型にするのかも重要です。借入額にもよりますが、定率型の場合、一時的な事務手数料の負担が大きくなる代わりに毎月の支払額は小さくなります。定額型の場合は事務手数料の負担が小さい代わりに毎月の支払額が大きくなります。金利と手数料を併せてシミュレーションを行い、総合的に借換え先の金融機関を比較することが大切です。
最後に、住宅ローン借換時の金融機関の選び方について紹介します。
住宅ローンの借換えにかかる手数料は、借換える金額によって、数十万円から100万円を超えることがありますので、なるべく抑えたいところです。ただ、金額の比較だけであれば「高い・安い」が判断軸となりますが、借換えの場合、借換えにかかる手数料と借換えによる利息負担の軽減をシミュレーションする必要があります。
住宅ローンの借換え予定金額や適用金利、残りの返済期間などが分かれば、WEB上で手軽にシミュレーションすることもできるサイトがありますので利用してみましょう。
また、借換えにおける金利や手数料以外では、団信の保障内容や繰り上げ返済のしやすさ、相談できる店舗などが比較のポイントになります。特に、団信については、がん団信をはじめさまざまな特約付団信があり、金融機関によって、加入できる年齢や金利上乗せ(保険料)、保障内容が異なります。借換時点の年齢や家計の状況によっても必要な保障は変わりますので、借換えの手続きを合わせて金融機関で相談されることをおすすめします。
住宅ローンの借換えにおいてまずすべきことは、借換え時の諸費用に対して利息軽減効果がどれくらいあるかシミュレーションすることです。そのうえで、金利水準を含めて、事務手数料や保証料などの諸費用が安い金融機関を選ぶことが大切です。
借換えの効果をシミュレーションするためには、現在利用中の住宅ローンの返済予定表と借換え予定の住宅ローン金利水準、借換金額、返済期間などの情報が必要となります。
ただし、借換え後の金利タイプや返済期間によってシミュレーション結果は変わるため、相談しながら進めたいというかたはSBIマネープラザへお越しください。
こんなかたには店舗相談がおすすめです
SBI マネープラザの店舗では、住宅ローンに詳しいスタッフがわかりやすく説明します。 ご予約することで待ち時間もなくご相談いただけます。
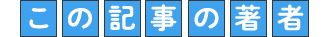

株式会社あつみ事務所 代表
建設会社・ハウスメーカーで建築設計、不動産売買仲介を経て、不動産・住宅専業ライターとしても活動。これまで不動産・金融メディアを中心に300本以上の記事執筆を手掛ける。現在、不動産売買や住み替えを中立的な立場でサポートするサービスを提供しながら情報発信を行う。
【保有資格】宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級技能士・住宅ローンアドバイザー