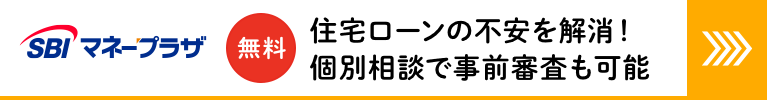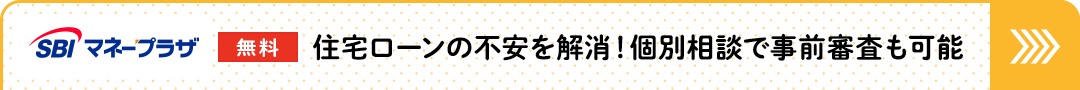住宅ローン審査の際、勤続年数が短いと、「審査に通らないのでは?」「希望する金額を借りられないのでは?」「融資条件が悪くなるのでは?」などと、心配になることもあるのではないでしょうか。
この記事では、住宅ローンと勤続年数の関係について以下の点を解説します。
勤続年数の短いかたが住宅ローン審査を受ける際、どういった点に注意し、どのように準備すればよいかわかりますので、最後までご一読ください。
住宅ローンの審査項目は多岐にわたり、総合的に判断されます。そのなかで、勤続年数は、住宅ローン審査にどれくらい影響するのでしょうか。
ここでは、勤続年数を重視する金融機関の割合や、求められる勤続年数などについて解説します。
「令和4年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」によると、「勤続年数」以外にも多くの項目が、住宅ローンの審査時に考慮されていることがわかります。
9割以上の金融機関が「考慮する」と回答した項目は下記の通りです(数値は回答した金融機関の割合)。
(回答数1,016件)
このように、勤続年数は審査項目の一つとして挙げられていますが、その他の項目も審査時に考慮されているようです。
続いて、金融機関が住宅ローンの申込者に求める勤続年数について見てみましょう。同じく、「令和4年度 民間住宅ローンの実態に関する調査」では下記の結果となりました(数値は回答した金融機関の件数)。
(回答数947件、複数回答)
このように、1年以上と回答する金融機関が最も多い結果となりました。
9割以上の金融機関が住宅ローン審査において考慮すると回答する勤続年数は、なぜ重要なのでしょうか。
住宅ローンは貸付金額が大きく返済期間も長いですが、金融機関はもちろん完済してもらう前提で融資を行います。そのため、融資を行うにあたってまず重視されるのが、住宅ローン契約者の返済能力です。
そのため勤続年数が短いと、「収入の安定性が低い」「継続的な返済が難しいのでは」と判断されやすい傾向にあるのです。また、年齢にもよりますが、転職したばかりの場合、継続して勤務しているかたと比べると昇給が遅い、退職金が少ないと判断される可能性もあります。
このように、長期の返済を伴う住宅ローン審査では、収入そのものの高さも大切ですが、収入の安定性も考慮されるために勤続年数が重視されると考えられます。
続いて、実際に住宅を購入したかたの平均的な勤続年数を統計資料から見てみましょう。
(下記の統計は住宅ローンの利用の有無を問わず、住宅を購入したかたに対して調査されたものです)
国土交通省が住宅ローンを利用したかたを含む、住宅の購入者に対して行った調査、「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によれば、三大都市圏における住宅購入時の平均勤続年数は12.1年~15.7年でした(※2)。
住宅の種類別で、購入者の平均勤続年数は次のようになっています。
【住宅の種類別 購入者の平均勤続年数(三大都市圏)】
| 住宅の種類 | 平均勤続年数 |
|---|---|
| 注文住宅 | 15.1年 |
| 分譲戸建て | 12.1年 |
| 分譲マンション | 15.7年 |
| 中古戸建て | 15.4年 |
| 中古マンション | 14.9年 |
この表をご覧になると、「イメージと少し違う」と感じられるかたもいらっしゃるかもしれません。この統計は文字通り「平均」であって、少数の回答者による回答次第では結果が上にも下にも大きく変動することがあります。
実態に近い数字を表すという意味では、次の統計結果のほうが参考になるかもしれません。
同じく「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によると、「勤続10年未満」と「勤続10年~20年未満」では、注文住宅と中古戸建てを除き、その差は2.0%以内であることがわかります。
住宅種別による違いはありますが、勤続10年未満の場合30~40%程度、そのうち勤続5年未満の割合が10~15%程度と、勤続年数が短いかたも一定数いることがわかります。
【住宅の種類別 購入者の勤続年数の割合(三大都市圏)】
| 住宅の種類 | 勤続5年未満 | 勤続5年~10年未満 | 勤続10年~20年未満 | 勤続20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 注文住宅 | 13.9% | 27.1% | 31.8% | 26.7% |
| 分譲戸建て | 15.3% | 22.7% | 36.3% | 17.6% |
| 分譲マンション | 10.6% | 17.8% | 35.2% | 30.7% |
| 中古戸建て | 15.4% | 17.8% | 32.0% | 31.7% |
| 中古マンション | 16.6% | 15.1% | 35.5% | 27.4% |
このような結果となりましたが、あくまで統計は全体の傾向であり、参考程度にとどめておくほうがよいでしょう。また、住宅ローンの審査において考慮されるのは勤続年数のみではありませんから、やはり勤続年数にとらわれすぎる必要はないと考えられます。
※2 出典:国土交通省「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」(調査対象:2021年4月~2022年3月に住み替え・建て替え・リフォームを行った世帯)
三大都市圏として首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)・中京圏(岐阜県・愛知県・三重県)・近畿圏(京都府・大阪府・兵庫県)における結果を対象としています。
住宅ローン審査では、借入の可否だけでなく、借入金額や状況によって適用金利も左右されますので、審査前に最大限の準備をすることが大切です。
それでは、住宅ローン審査時に勤続年数が短くて不安な場合、どのような対策が考えられるのでしょうか。
転職して間もない場合、前職での勤続年数を合算できることがあります。
例えば、同じ業界、同職種の企業への収入アップが伴う転職や、スキルアップのための転職、前職より財務内容の良い企業への転職などは、前職と転職後の勤続年数の合算を考慮してもらいやすい傾向があります。
また、税理士や公認会計士、弁護士といった収入の安定性が高い資格を取得しての転職であれば、転職に対する金融機関からのマイナス評価を受けにくい場合があります。
勤続年数が短いだけでは、必ずしもマイナス評価になるとは限らないので、金融機関に相談、交渉してみましょう。
勤続年数が短い場合、それ以外の条件で補えるものがないか確認しておくことも大切です。
住宅ローン審査ではさまざまな項目によって総合的に判断されますので、勤続年数のマイナスを補えるポイントが多ければ審査に有利になります。
例えば、頭金を増やすことで住宅ローンの借入金額が減ると、審査項目である返済負担率や融資率の評価がプラスになります。融資率は、物件価格に対して借入金額が占める割合を指し、金融機関の約7割が審査にあたって考慮すると回答しています。
また、借入金額が減ることで返済期間を短くできれば、最も多くの金融機関が考慮する、完済時の年齢を早められる場合もあるでしょう。
ペアローンや収入合算を利用できれば、審査の対象となる収入が増えるだけでなく、互いに連帯保証人や連帯債務者となりますので、審査上有利になります。
勤続年数や雇用形態が住宅ローンの申込条件となっていない、フラット35を利用する方法もあります。
フラット35は、民間の住宅ローンとは異なり、審査において人的審査より物件審査が重視される傾向にあります。
そのため、転職間もないケースでも収入があれば、住宅ローンに申し込め、問題なく通ることもあります。
ただし、転職して3ヵ月以内など、勤務期間があまりに短い場合、直近の給与明細を求められるなど、審査が慎重に進められることもあります。
勤続年数が短くても活用できるフラット35について、次の章で解説します。
>>あわせて読みたい 「フラット35とは?」利用条件やメリット・デメリットを解説!
勤続年数が短く、民間の住宅ローンの利用が難しいケースでも活用しやすいフラット35ですが、勤続年数以外の条件もあります。
ここでは、フラット35利用にあたって知っておきたい基礎知識やメリット・デメリットについて解説します。
フラット35では勤続年数に関する申込要件がありませんが、それ以外に次のような条件があります。
<フラット35の主な申込要件>
■ 申込時の年齢が満70歳未満、完済時年齢が80歳未満のかた(親子リレー返済利用時は満70歳以上も可)
■ 日本国籍のかた、永住許可を受けているかた、または特別永住者のかた
■ すべての借入れに関して、税込年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たすかた
・年収400万円未満の場合…総返済負担率30%以下
・年収400万円以上の場合…総返済負担率35%以下
>>その他の申込要件については、こちらの記事で紹介しています!
フラット35は、返済期間中に金利の変動しない全期間固定金利型の住宅ローンで、全国300以上の金融機関が取扱っています。金融機関ごとに借入金利などの借入条件も異なりますので、あわせて確認しておきたいポイントになります。
続いてフラット35のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
メリット① 借入時点の金利で固定される
借入時に返済終了までの借入金利と返済額が確定されるので、返済計画やライフプランを立てやすくなります。
メリット② 保証料が不要
フラット35では保証会社を利用しないため、住宅ローンの諸費用の中では比較的高額になりやすい保証料が不要です。
メリット③ 選べる団体信用生命保険
フラット35に付帯できる団体信用生命保険(以下、「団信」)には、死亡や所定の身体障害に備える「新機構団信」に加え、3大疾病にも備えられる「3大疾病付機構団信」、連帯債務者となる配偶者も保障の対象となる「ペア連生団信」のラインナップがあります。
| 団体信用生命保険 | 保障内容 | フラット35の借入金利 |
|---|---|---|
| 新機構団信 | 死亡・所定の身体障害 | 新機構団信付きのフラット35の借入金利 |
| 新3大疾病付機構団信 | 死亡・所定の身体障害 がん・急性心筋梗塞・脳卒中を発病しそれぞれ住宅金融支援機構が定める基準の状態 公的介護保険制度が定める要介護2~5の状態 |
新機構団信付きのフラット35の借入金利+0.24% |
| ペア連生団信(デュエット) | 申込本人または配偶者の死亡・所定の身体障害 | 新機構団信付きのフラット35の借入金利+0.18% |
(2020年12月現在)
フラット35のデメリット
フラット35のデメリットとしては、①借入金利が相対的に高い、②借入以降に市場金利が低下しても借入金利は変わらない、③購入する住宅に関して独自の基準がある、といったことが挙げられます。
>>あわせて読みたい フラット35のデメリットとは? メリットと併せて知っておきたい点
ここまで、住宅ローン審査時の勤続年数の実態や勤続年数が短い場合の対策などについて解説してきました。
最後に、住宅ローンと勤続年数に関するよくある質問を紹介します。
勤続年数が半年でも住宅ローンを組むことはできます。
大手銀行も含め、勤続年数3ヵ月以上から審査対象となる金融機関や、勤続年数の条件はなく、勤務先の属性等によって個別に判断する金融機関もあります。
申込み予定の金融機関の審査条件について、金融機関もしくは不動産会社や住宅業者を通じてしっかりと確認、対策したうえで申込みしましょう。
住宅ローン申込みにおいて、勤務先の入社年月日を申告しますが、この際に嘘の申告をしても発覚しますので、正直に申告しましょう。
金融機関は、入社年月日を証明する資料と申告内容が一致しているかを確認します。嘘の申告が発覚した場合、審査結果に影響するだけでなく、審査に通らない、審査対象から外れる可能性もあります。
住宅ローン審査では、一般的に、健康保険証に記載される資格取得日で勤続年数の確認を行います。住宅ローン申込書に記載する入社年月日や就職年月日と健康保険証の日付にズレがないかを確認するのです。
ただし、グループ企業などに転籍・出向した場合などは、健康保険証の資格取得日と入社年月日が異なる場合がありますので、審査に申込む段階でその旨を伝えておきましょう。
倒産やリストラといった会社都合による転職であっても、原則として、住宅ローン審査では通常の転職扱いとなり、転職後の勤続期間が審査対象となります。
金融機関は融資にあたって、収入の継続性や安定性という意味で勤続年数を考慮する傾向にありますので、会社都合であっても、勤務先の規模や財務内容、雇用形態を含め、安定性を重視して判断すると考えられます。
住宅ローン審査において、勤続年数は重要な審査項目です。
ただし、住宅ローン審査では、ほかのさまざまな項目を含めて総合的に審査するため、勤続年数は返済能力を判断する1つの材料にすぎないともいえます。
そのため、住宅ローン審査にあたって、金融機関の申込条件をしっかり確認するとともに、勤続年数以外の条件について、最大限の対策を考えることが大切です。
また、前職での勤続年数を通算できる場合や、転職自体がマイナスポイントにならないと考えられる場合は、その点について金融機関と交渉できるよう、しっかり準備しましょう。
こんなかたには店舗相談がおすすめです
SBIマネープラザの店舗では、住宅ローンに詳しいスタッフがわかりやすく説明します。ご予約することで待ち時間もなくご相談いただけます。
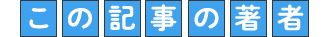

株式会社あつみ事務所 代表
建設会社・ハウスメーカーで建築設計、不動産売買仲介を経て、不動産・住宅専業ライターとしても活動。これまで不動産・金融メディアを中心に300本以上の記事執筆を手掛ける。現在、不動産売買や住み替えを中立的な立場でサポートするサービスを提供しながら情報発信を行う。
【保有資格】宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級技能士・住宅ローンアドバイザー