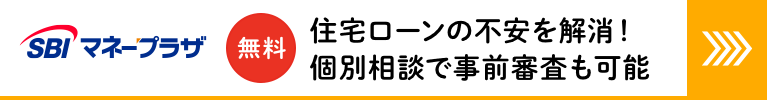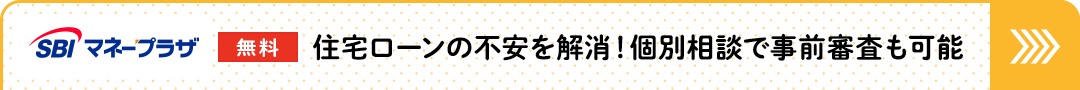長期間に及ぶ住宅ローンの返済期間中、自分が住宅ローンを借りたときよりも金利が下がっているのを見て、自分ももっと低い金利で借り直せないかと考えているかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合に検討できるのが、現在の住宅ローンからほかの金融機関の住宅ローンへの借り換えです。
ただし、大きな資金の借入先を変更することになる住宅ローンの借り換えには、注意すべき点もあります。
この記事では、住宅ローンを借り換えるにあたっての注意点や、後悔しないためのポイントについて解説します。
ここでは、住宅ローンを借り換えるとどうなるのか、借り換えの仕組みから、借り換える理由までを解説し、住宅ローンの借り換えを積極的に検討すべきなのはどのような場合なのかを考えていきたいと思います。
住宅ローンの借り換えとは、現在借り入れている住宅ローンをほかの金融機関で借り入れした資金で一括返済する手続きです。
「借り換え」と聞くと、借り入れする金融機関が変わるだけというイメージを持たれるかたもいますが、契約内容や返済計画を変更できる場合もあります。
また、手続きとしても、現在の住宅ローンを完済する、新たな借入先金融機関の審査を受けて契約する、といった一連の手続きが必要となります。
住宅ローンを借り換える理由は、いくつか考えられます。
返済中の住宅ローンよりも低い金利で借り換えることができれば、返済計画や金利動向によりますが、毎月の返済額、完済までの総返済額を減らすことができます。
特に、固定金利タイプの住宅ローンを契約中のかたは、変動金利タイプに変えることで、返済額を大きく減らせるかもしれません。
ただし、今後の金利上昇リスクと引き換えになるため、単純に返済額だけを見ずに慎重に検討する必要があります。
金利上昇のリスクを減らす、あるいはなくすために、変動金利タイプから全期間固定や固定期間選択型の金利タイプに切り替えることも考えられます。
金利動向を正確に予想することはできませんが、物価上昇や日銀の金融政策の見直しを受け、金利上昇に備えたいというかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
固定金利に借り換えることで、変動金利で借りていた時より借入金利が高くなったとしても、将来的には返済額を抑えられる可能性もあります。
また、固定金利であれば返済額を一定に保つことができるため、完済の時期を含めて、リタイア後に向けての返済計画を立てやすくなるというメリットもあります。
借り換えの際に、返済期間や返済方法、団体信用生命保険(以下「団信」)の保障内容を見直すこともできます。
例えば、同じ借入金額でも借り換え前より返済期間を長く設定できた場合、毎月の返済額を抑えることができます。
また、金融機関によって団信に付帯する保障は異なるほか、現在の住宅ローン契約時には不要だと思った特約に加入したり、逆に不要だと思った特約に加入しないことで支払額を抑えたりすることもできます。
ただし、借り換え時の健康状態によっては特約に加入できないまたは保険料が高くなることや、そもそも団信に加入できないこともあるので注意が必要です。
以上を踏まえて借り換えを検討する前に注意すべき点もあります。
住宅ローン控除の適用期間がまだ残っている場合、借り換え後も引き続き控除を受けられるかどうか、注意する必要があります。
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%(借入時期によっては1.0%)を上限に、所得税や住民税の一部から控除できる制度です。
住宅ローン控除の経済的メリットは大きく、借り換えで返済額を抑えられたとしても住宅ローン控除を受けられなくなり、かえって損をしてしまうということが無いように気を付けましょう。
住宅ローン控除を借り換え先の金融機関でも引き続き受けるための要件は次の2つです。
借り換えにあたって、借入金額や返済期間などを変えることもできますが、住宅ローン控除を受けるためには返済期間が10年以上でなければならない点、ローン残高が住宅ローン控除額に影響する点には注意してください。
借り換え先の審査に通る必要があるため、借り換え時点の収入に見合った借入額かをしっかりと確認することが必要です。
住宅ローン審査においては、完済時の年齢のほか、返済負担率(年収に対して年間の住宅ローンやその他ローンの返済額が占める割合)は重視される傾向にあります。元の住宅ローンを契約したときにはなかったカーローンや教育ローンなどを返済中の場合は特に注意すべきでしょう。
ほかにも、元の住宅ローンを契約したときから年齢だけではなく収入・ご職業なども変わっていることがあるほか、金融機関が異なれば審査基準も異なるので、審査を通過できないこともあります。
借り換えにあたっては、改めて団信に申し込むことが必要となります。
健康状態によっては、生命保険会社の審査に通らず借り換えができないことがありますので、不安のあるかたは早めに借り換える先の金融機関へ相談してみましょう。
住宅ローン返済以外の借り入れについても、支払いの遅滞などがないか確認しましょう。
金融機関は審査にあたり、住宅ローン返済だけでなく、クレジットカードや各種ローン、スマートフォンなどの分割購入の履歴も含めてチェックします。
もし延滞があった場合でも、時期や延滞期間、回数などで、金融機関の評価は分かれます。
借り換えを行う際には、現在借り入れをしている金融機関に支払う完済手数料や借り換え先の金融機関に保証料・手数料、登記に関する費用が必要となり、借り入れ金額と借り換え先の金融機関によっては、数十万円から数百万円程度の費用が発生します。
また、借り換えの際にはこれらの手数料も含めて借り換えられるものもありますので、諸費用を含め借り換えメリットを総合的に考えましょう。
住宅ローンの借り換えでは、住宅ローンの金利タイプや返済期間なども決める必要があります。ここでは、借り換えで後悔しないためのポイントについて解説します。
後悔がないように、借り換えするにあたっては、複数の金融機関を比較・検討しましょう。
金利だけでなく、借り換えに伴う事務手数料や諸費用、団信の内容も金融機関によって異なります。
返済額を減らすために適用金利を比較することは大切ですが、金利だけで判断してしまうと後悔するかもしれません。借り換え前に、複数の金融機関をしっかりと比較・検討してから決めましょう。
借り換えの際には、返済額のシミュレーションをすることが大切です。
借り換えに併せて、金利だけでなく借入金額や返済期間を変えられる場合もあり、返済計画次第で毎月の返済額や総返済額も変わります。
借り換え前の返済額からどれくらい変わるのか、借り換えに伴う諸費用も含めて、しっかりとシミュレーションする必要があります。
また、借り換え前よりも毎月の返済額が少なくなる一方、完済の時期は遅くなるケースや、返済額を減らせる一方、団信の保障内容が手薄になるという場合もあるでしょう。
目的に応じて、借り換えによるメリットとデメリットをしっかりと比較することが大切です。
【住宅ローン借り換えの注意点】
こういった点を踏まえ、返済額や団信などについて複数の金融機関を比較・検討するとともに、借り換えにかかる諸費用を含めて、借り換え前後の返済額をシミュレーションすることが大切です。
それらも踏まえて借り換えをすべきかどうかを判断しましょう。
数多くの住宅ローン商品があるなか、借り換えによってどれくらいのメリット、あるいはデメリットがあるのかを判断するのは簡単ではありません。
SBIマネープラザでは、お客さまの借り換えの目的に合わせて、借り換え前後の返済額のシミュレーションや返済プランの無料相談を受け付けています。
来店相談だけでなく、店舗によってはオンライン相談も可能ですので、「借り換えを検討している」「借り換えのメリットはどれくらいか知りたい」というかたはお気軽にお問い合わせください。
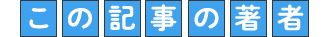

株式会社あつみ事務所 代表
建設会社・ハウスメーカーで建築設計、不動産売買仲介を経て、不動産・住宅専業ライターとしても活動。これまで不動産・金融メディアを中心に300本以上の記事執筆を手掛ける。現在、不動産売買や住み替えを中立的な立場でサポートするサービスを提供しながら情報発信を行う。
【保有資格】宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級技能士・住宅ローンアドバイザー