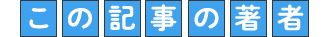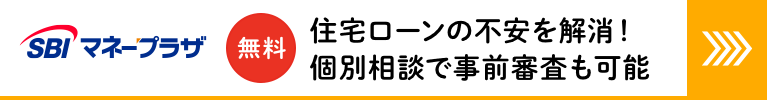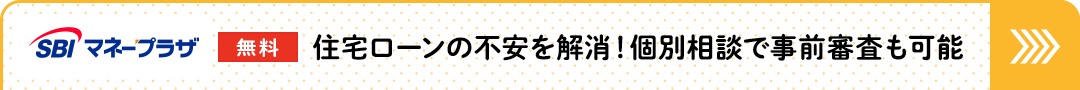住宅ローンの契約をする際、場合によっては連帯保証人を立てることがあります。特に、ペアローンを組む場合や収入合算で住宅ローンを組む場合は、契約にあたってペアや収入合算する相手が連帯保証人になることが必要となるのが一般的です。
今回は、住宅ローンを締結するにあたって連帯保証人が果たす役割や責任、確認すべきことなどを解説します。
一般的に、住宅ローンを契約する際に連帯保証人は必須ではありません。まずは、連帯保証人が必要になる場合や連帯保証人が果たすべき義務など、基本的な内容から見ていきましょう。
住宅ローンの連帯保証人とは、住宅ローンの契約者(主たる債務者)がローンを返済できなくなった場合に、代わりに借金を返済する義務を負う人のことです。契約者が返済を延滞した場合には、連帯保証人は金融機関から返済を求められます。
「連帯保証人」と似た言葉で「保証人」「連帯債務者」があります。住宅ローンにおけるそれぞれの違いをまとめると、以下のようになります。
| 概要 | ポイント | |
|---|---|---|
| 保証人 | 契約者が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う | 契約者に返済能力がある場合、返済を拒否できる |
| 連帯保証人 | 契約者と同等の返済義務を負う | ・連帯保証人は住宅ローン控除を受けられない ・契約者の返済能力に関係なく、返済を拒否できない |
| 連帯債務者 | 契約者と共に1つの住宅ローンを返済する |
・連帯債務者も住宅ローン控除を受けられる ・契約者の返済能力に関係なく、返済を拒否できない |
保証人は、金融機関から返済の請求を受けても、まずは主たる債務者本人に請求するように要求することや、債務者本人の財産に対して強制執行をするように要求することができます。債務者が返済できなくなった場合に限り、債務者の代わりに返済する義務を負います。
連帯保証人は、債務者と同等の返済義務を負います。債務者の返済能力に関係なく、金融機関から返済を求められたら拒否できません。
連帯債務者は、保証人ではなく債務者です。債務者として、契約者と共にローンを返済しなければなりません。ただし、連帯保証人と違い、連帯債務者は住宅の所有権を登記した際の持分割合と住宅ローンの返済負担割合に応じて、住宅ローン控除を受けられます。
現在は、ほとんどの住宅ローン契約において、連帯保証人は求められません。金融機関がローンの対象となる不動産に抵当権を設定し、回収できなくなるリスクに備えているためです。
また、住宅ローンの契約で連帯保証が必要になった場合でも、通常は保証会社を利用します。保証会社が連帯保証人の代わりを務めるため、連帯保証人を立てられなくても、住宅ローンの契約を締結できるのが一般的です。
連帯保証人が必要となるケースについてご紹介します。
ペアローンとは、夫婦や親子などが契約者となり、同じ物件に対して2本の住宅ローンを組むことです。たとえば、5,000万円の住宅ローンを組む際に「夫:2,500万円、妻:2,500万円」「夫:3,000万円、妻:2,000万円」のように、それぞれが住宅ローンを契約します。
ペアローンの場合、それぞれの住宅ローンに対して、お互いが連帯保証人となります。つまり、夫の住宅ローンに対しては妻が連帯保証人に、妻の住宅ローンに対しては夫が連帯保証人になるのが一般的です。
収入合算とは、夫婦や親子などの収入を合算して住宅ローンを組むことです。二人分の収入を基に融資する金額が決定され、どちらかが住宅ローンの契約者となり、もう一方が連帯保証人となります。
ペアローンとは異なり、住宅ローン契約は1本です。
購入する不動産を共有名義にする場合は、連帯保証人を求められるのが一般的です。共有によって契約者の持ち分の割合が減ってしまうと、担保価値が不十分となる可能性があるためです。
たとえば、住宅購入時の頭金を妻が負担して夫が住宅ローンの契約者になる場合、物件は夫婦の共有名義となります。このケースでは、夫が契約者であるのに対し、共有名義者である妻が連帯保証人となり、夫と同等の返済義務を負わなければなりません。
審査の結果「返済能力が不十分である」と評価された場合、連帯保証人を求められるケースがあります。契約者が住宅ローンの返済不能になった場合、融資したお金を回収できないリスクに備えるためです。
たとえば、自営業者や勤続年数が短い人は「収入が不安定」「収入が低い」という理由で、返済能力を疑問視される可能性があります。また、希望している借入金額に対して収入が不足している場合も、連帯保証人を立てることを条件とされるケースもあります。
連帯保証人が必要になった際に押さえておくべきポイントについて解説します。
連帯保証人は、契約者が住宅ローンを払えなくなったときに返済義務を負います。経済的にも精神的にも大きな負担がかかることになり、金銭トラブルに発展するリスクも考えられるでしょう。
・離婚・死亡しても一方的に連帯保証人から外せない
債権者である金融機関の承諾を得ない限り、離婚や契約者の死亡など、家庭事情が変化しても連帯保証人から外れることはできません。
自分が連帯保証人となって住宅ローンを締結したあとは、契約者と離婚しても連帯保証人であり続けます。離婚後も、契約者が返済できなくなったら連帯保証人として返済義務を負わなければならないのです。
また、離婚の際に自宅を売却する場合も、売却代金と自己資金で住宅ローンを完済できなければ、以降も返済を続けなければなりません。
また、連帯保証人が死亡しても、法定相続人に債務が引き継がれるため、相続人が新たな連帯保証人となります。
連帯保証人は一度引き受けると一方的に外れることはできません。重い責任を負うため、連帯保証人を「頼む側」と「引き受ける側」の双方がしっかりと仕組みを理解しましょう。
・連帯保証人が自己破産した場合、契約者は一括返済を求められることがある
連帯保証人が自己破産して支払能力がなくなった場合、代わりの連帯保証人を立てるまたは住宅ローン残債の一括返済を求められる可能性があります。
ただし、契約者が滞りなく返済できていれば、直ちに一括返済を求められる可能性は低いのが一般的です。不安があれば、契約している金融機関で相談するとよいでしょう。
前述した通り、連帯保証人から外すのは簡単ではありません。
ただし不可能ではないため、具体的にどのようなケースが該当するのかを見ていきましょう。
・住宅ローンの借り換えを行う
現在契約している金融機関とは異なる金融機関で住宅ローンの借り換えを行うことで、連帯保証人を外す方法があります。借り換えは新しい住宅ローンを契約することを意味するため、連帯保証人が不要の住宅ローンに借り換えれば、連帯保証人を外すことが可能です。
・住宅ローンを完済する
住宅ローンを完済できれば、連帯保証人の必要がなくなります。手元に十分な資金がある場合、検討するとよいでしょう。
完済できない場合でも、住宅ローン残高が一定金額を下回った場合、連帯保証人を外せるケースもありますので、契約している金融機関に相談してみるのがよいでしょう。
ペアローンや収入合算で住宅ローンを組む場合、ペアローンや収入合算する相手に連帯保証人になることを求められるのが一般的です。住宅ローンを契約する際に連帯保証人を求められたら、連帯保証の仕組みや負うべき義務・責任をあらためて確認しましょう。
連帯保証人は契約者と同等の責任を負うため、どのようなリスクが考えられるのかを慎重に考える必要があります。不安や疑問があれば、住宅ローンの専門家に相談することをおすすめします。
SBIマネープラザでは、毎月の返済額や借入金額の目安などの情報を得られるだけでなく、連帯保証人をつけて契約するメリットやリスクなども相談できます。自分に合った住宅ローンの契約方法でお悩みの方は、お気軽にご利用ください。