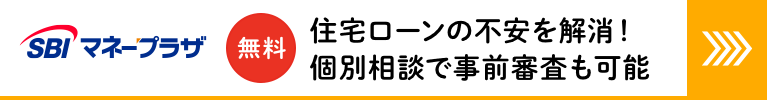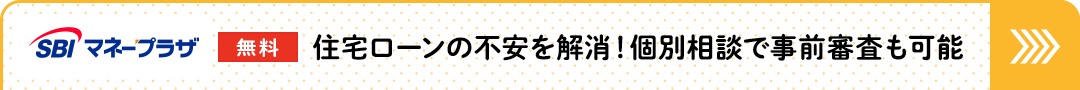マイホームの資金計画を考える際、購入予算は住宅ローンをいくら借りるかによって変わり、物件選びにも影響します。
しかし、初めて住宅を購入する方も多く、自分にとって適正な借入金額を判断することは簡単ではありません。住宅ローン審査を受けることで借入可能額自体はわかりますが、それが必ずしも適正な借入金額とは限らないのです。
そこで、適正な住宅ローン借入金額を判断する指標として、「返済比率」があります。
この記事では、返済比率の意味や計算方法、年収別・借入金額別の返済比率について解説します。
まずは、返済比率の意味や計算方法、年収に対する目安についてみてみましょう。
返済比率は総返済負担率とも呼ばれることがあり、「年収に占める年間返済額の割合」を指します。返済負担率は以下の計算式によって算出されます。
返済比率(%)= 年間の返済額の合計 ÷ 額面年収 × 100
例えば、額面年収600万円のかたが、年間120万円の返済を行っている場合、
返済比率(%)= 120 万円 ÷ 600 万円 × 100 = 20.0%
となります。
ただし、年間の返済額は、新たに利用しようとしている住宅ローンだけでなく、その他の借入れの年間返済額を足して計算します。たとえば、現在自動車ローンを返済しているとしたら、その自動車ローンの年間返済額と、新たに借入しようとしている住宅ローンの年間返済額を足して、年間の返済額とします。
この返済比率が高ければ高いほど、金融機関の住宅ローンの審査はより厳しい視点で見られやすく、また生活面では家計における各種のローンの負担が重くなることを示しています。
返済比率の上限は金融機関によって異なり、住宅ローン借入時の返済比率の上限を定めているところもあります。例えば、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35においては、返済比率(総返済負担率)は、下記の基準が設けられています。
年収400万円未満の場合:返済比率30%以下
年収400万円以上の場合:返済比率35%以下
ただし、借入金額や返済額を検討するうえでは、返済比率の上限が、必ずしも無理のない返済可能な水準とは限りませんので注意が必要です。例えば年収400万円のかたの場合、フラット35ならば返済比率の上限(※)を金額にすると「400万円×35%=140万円」、月額に直すと約11.6万円ですから、返済が難しいと感じるかたもいらっしゃるでしょう。
それでは、無理のないゆとりある返済計画とするには、返済比率をどのように考えるとよいでしょうか? 一般的には25%以内の返済比率を目安にするとよい、とする考え方もありますが、家族構成などを考慮せず一律に線引きするのではなく、将来のライフプランを考慮して借入金額や返済比率を検討することが重要となります。
次の章では、その際の目安となるよう年収別のシミュレーションを基に説明します。
※返済比率の上限は金融機関によって異なります。
ここでは、借入金額が増えると返済比率がどのように変わるのか、シミュレーションツールを使用して試算し、年収別に解説します。
<共通条件>
借入期間:30年
借入金利:年率1.5%
金利タイプ:全期間固定金利
返済方式:元利均等返済
ボーナス返済:なし
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 31.20% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 36.30% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 41.70% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 46.80% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 51.90% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収400万円の場合、借入金額3,000万円の返済比率が31.20%と、一般的に無理のない返済比率といわれる25%をすでに超えています。
返済比率が高い場合、住宅ローンの借り入れができたとしても、金利変動や家計の変化といった状況の変化に対応しにくい点には注意が必要です。
返済比率を25%以内に収めるためには、借入金額を2,414万円以内に抑える必要があります。ただし、返済プランとして、借入期間を試算の前提条件とした30年ではなく、35年で組むことができれば、2,721万円まで借入金額を上げることができます。
資金計画に対して借入金額が足りない場合、配偶者に収入があれば、収入合算やペアローンを利用して借入金額を増やすことも考えられますが、世帯収入に対して借り過ぎになっていないかどうか注意する必要があります。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 24.96% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 29.04% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 33.36% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 37.44% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 41.52% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収500万円の場合、<共通条件>を前提に3,000万円を借入れると、毎月の返済額は10.4万円となります。また返済比率は24.96%と計算され、目安と言われる25%を下回っています。借入金額が増えると返済比率も上昇し、借入金額が4,500万円、5,000万円の場合はフラット35の基準である35%を超えるため、フラット35は利用できないことがわかります。
「返済比率の基準を満たせない」「毎月の返済の負担が重い」という場合には、借入金額を下げたり、借入期間を延ばしたりするなどの対応が考えられます。上記のシミュレーションでは、借入金額4,500万円でも借入期間を30年から35年に延ばすことで、毎月の返済額は13.8万円、返済比率は33.12%となるため、フラット35の基準を満たすことが可能となります。
そのうえで、現在の生活費や将来の支出を考慮して、現実的な借入金額と借入期間を検討するとよいでしょう。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 20.80% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 24.20% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 27.80% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 31.20% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 34.60% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収600万円の場合、借入期間30年でも<共通条件>が前提ならば、フラット35の基準では5,000万円を借入れるための返済比率の水準を満たすことができます。
ただし、返済比率の水準を満たしていても、返済計画に無理が生じやすいと判断される場合には、頭金を多めに準備して借入金額を下げたり、借入期間を延ばしたりするなどの対応を考えましょう。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 17.83% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 20.74% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 23.83% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 26.74% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 29.66% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収700万円の場合、<共通条件>の前提であれば、借入金額5,000万円でも返済比率は30%を下回ります。さらに借入期間を35年に延ばすと、毎月の返済額は15.4万円、 返済比率は26.40%まで下がりますから、毎月・毎年の返済金額にゆとりができます。
ただし前述の通り、返済比率は目安と考え、住宅ローンの返済以外の生活費や将来の支出を考慮して借入金額や借入期間を検討するようにしましょう。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 15.60% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 18.15% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 20.85% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 23.40% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 25.95% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収800万円になると、借入金額が5,000万円でも返済比率25.95%と、無理のない返済比率の目安である25%に近い数字となります。返済プランとして、借入期間を30年ではなく35年にできれば、返済比率は22.95%に収まります。
また、借入期間35年、返済比率25%以内とする場合、5,443万円まで借入可能となるなど、返済プランによっては借入金額のアップも検討できるでしょう。
ただし、借入金額は、住宅ローンの返済比率だけなく、家計の支出状況や必要な貯蓄なども併せて考える必要があります。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 13.86% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 16.13% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 18.53% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 20.80% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 23.06% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収900万円になると、5,000万円の借り入れでも返済比率は23.06%となり、無理のない返済比率の目安である25%に収まります。返済比率25%とした場合の借入金額は、5,432万円です。
さらに、借入期間を30年ではなく35年にすると、返済比率25%の借入金額は6,123万円となります。
借入金額は返済比率だけでなく、世帯収入や生活費、必要な貯蓄額なども考慮しながら判断する必要がありますが、返済プランによっては6,000万円を目安に借入金額を増やすこともできるため、物件選びの選択肢を広げることも可能でしょう。
| 借入金額 | 毎月の返済額 | 年間返済額 | 返済比率 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 10.4万円 | 124.8万円 | 12.48% |
| 3,500万円 | 12.1万円 | 145.2万円 | 14.52% |
| 4,000万円 | 13.9万円 | 166.8万円 | 16.68% |
| 4,500万円 | 15.6万円 | 187.2万円 | 18.72% |
| 5,000万円 | 17.3万円 | 207.6万円 | 20.76% |
(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用してSBIマネープラザが作成。手数料、その他の諸費用は計算に含まれていません)
額面年収1,000万円の場合、借入金額5,000万円に対する返済比率は20.76%であり、返済比率だけを見ると余裕があります。返済比率が25%になる借入金額は6,036万円のため、6,000万円の借り入れも検討できるでしょう。
返済比率が低い資金計画の場合、家計に対する住宅ローン返済の負担が小さいため、金利上昇などのリスクにも対応しやすくなります。
今回は、全期間固定1.5%で試算していますが、変動金利タイプを含め、より良い条件の住宅ローン商品を選ぶことで負担を抑えることができるでしょう。
>>SBIマネープラザの店舗で相談できることとは? スタッフインタビュー記事を読む
続いて、返済比率から借入金額を検討する際の注意点を見ていきましょう。
家庭によって生活費の金額は異なるのと同様、適正な返済比率も家庭によって異なります。家庭の支出は、世帯人数や生活様式、子どもの教育費などによって左右されます。そのため、同じ年収で同じ返済比率であっても、住宅ローンの返済負担の感じ方は異なるでしょう。
借入金額を検討する際には、生活費や教育費、貯蓄額等を考慮し、借入後も無理のない生活が続けられるような金額を設定する必要があるでしょう。
>>あわせて読みたい(「住宅ローン利用時に頭金はいくら用意する?」平均額と検討ポイント)
カードローンや自動車ローンなど、新たに借入れる住宅ローン以外の借入れがある場合には、それらのローンと住宅ローンの年間返済額の合計がいくらになるか把握しておきましょう。
住宅ローンの返済のみで考えると余裕があっても、その他の借入れを加えた全体では、返済の負担を大きく感じる場合があります。
そういった場合は、預貯金等で既存の借入れを完済してから、住宅ローンの申込みをしたほうがよい場合があります。なぜなら一般的には、住宅ローンの金利のほうがカードローンや自動車ローンなどの他のローンの金利よりも低く設定されているためです。また、住宅ローン控除のような税制優遇制度は他のローンには現状ないことも、その理由のひとつになります。
返済比率は、住宅関連費用のうち、住宅ローンの返済部分しか考慮されていません。しかし、マイホームを購入すると、住宅ローンの返済以外にも固定資産税、さらにはマンションの場合は修繕積立金や管理費などの費用がかかることもあります。もちろん、マイホームにて家具調度や家電等を充実させるならば、そのための費用も考慮する必要があるでしょう。
これらの費用も発生することを考慮のうえ、借入金額を検討するとよいでしょう。
>>あわせて読みたい(住宅ローンの月々の返済額の目安は? 借入額を検討するときの注意点)
住宅ローンの借入金額を検討する際、返済比率は重要な指標です。住宅購入にどの程度お金をかけるかは人それぞれのため、「無理がない」と考える返済比率も、人によっては25%ではなく、20%などに変わることもあるでしょう。
また、返済比率には、住宅ローン金利や借入期間などを反映させることができる一方、世帯ごとに異なる家計の支出(ライフスタイル)や必要貯蓄額などは反映させることができません。
住宅ローンは長期間の返済を前提とするため、返済期間中、お子さまの成長などに合わせて家計の状況が変わり、返済の負担感が変わることもあります。
住宅ローン借入金額は、返済比率を1つの基準としながら、ライフプランも含めて判断するようにしましょう。
こんなかたには店舗相談がおすすめです
SBIマネープラザの店舗では、住宅ローンに詳しいスタッフがわかりやすく説明します。ご予約することで待ち時間もなくご相談いただけます。
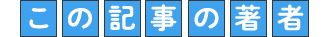

株式会社あつみ事務所 代表
建設会社・ハウスメーカーで建築設計、不動産売買仲介を経て、不動産・住宅専業ライターとしても活動。これまで不動産・金融メディアを中心に300本以上の記事執筆を手掛ける。現在、不動産売買や住み替えを中立的な立場でサポートするサービスを提供しながら情報発信を行う。
【保有資格】宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級技能士・住宅ローンアドバイザー