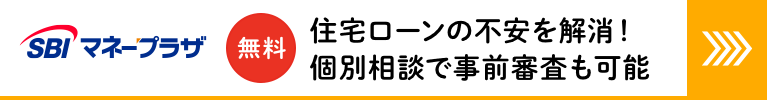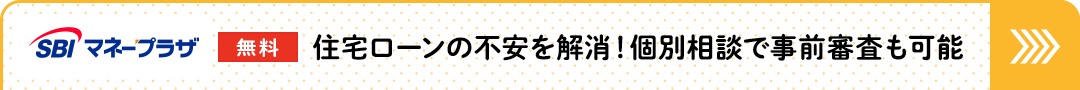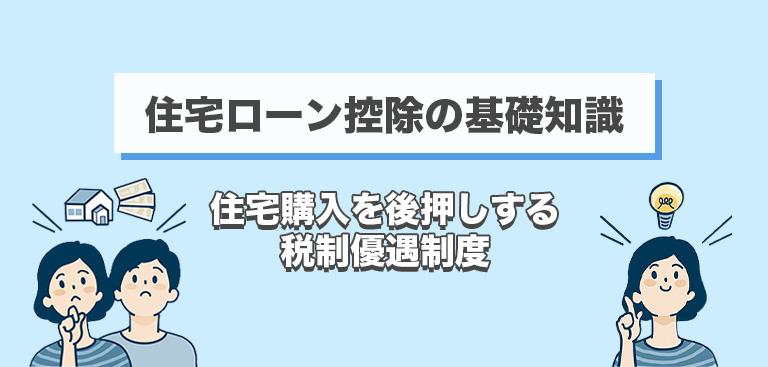
人生で一番大きな買い物といわれるのが「住宅」。昨今では、住宅ローンをより広く活用して購入の検討をされるのが一般的です。住宅ローンを返済されているかたは、所得税・住民税の還付が受けられる制度の「住宅ローン控除」は、ご存知のかたも多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、課税される所得を減らすことができる「所得控除(生命保険料控除や個人型確定拠出年金など)とは異なる税額控除(算出された所得税から控除を受ける)」ですから、個人が受けられる税制優遇制度の中では金額的に大きなウエイトを占めることになります。今回は住宅ローン控除の基礎知識と申請方法をご紹介します。
住宅ローン控除は、マイホーム購入という大きな負担を軽減し、住宅取得や増改築等を後押しするために国が設けている税制優遇制度です。
毎年年末時点の住宅ローンの残債の0.7%分が、所得税または一部翌年の住民税から最大13年間差し引かれます。
令和4年度の税制改正により、令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅については、住宅の省エネ性能が必須となりました。それ以前は、省エネ基準に適合しない住宅でも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができましたが、現在は住宅ローン減税の申請時に省エネ基準以上の適合であることの証明書が必要です。
また、住宅の性能(省エネ性能など)や入居した年によって借入限度額が定められており、この限度額を超える残高に対しては控除が適用されません。
<住宅ローン控除の概要(令和7年度税制改正後)>
| 新築/既存等 | 住宅の環境性能 | 借入限度額 (令和6・7年入居) |
控除期間 | 床面積 |
|---|---|---|---|---|
| 新築住宅 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500~5,000万円 | 13年間 (※1) |
50m2 (※2) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500~4,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000~4,000万円 | |||
| 既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 10年間 | |
| その他の住宅 | 2,000万円 |
<その他の主な要件>
① 自らが居住するための住宅例えば、以下の条件で住宅ローン控除のシミュレーションをしてみます。
毎月の返済額は112,914円、2025年11月から返済を開始しているので、
借入額4,000万円 ー 返済済金額159,228円(11~12月分)= 39,840,772円
住宅ローン控除は年末時点の住宅ローン残高の0.7%のため、
39,840,772円 × 0.7% = 278,885円
(※元金部分は概算、端数切り捨て)
2025年度の控除額は、278, 885円となります。その後も、一定の条件を満たせば最大13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から減額されることになります。
控除が受けられる金額よりも所得税そのものが少ない場合は、所得税からだけでなく、さらに住民税からも差し引くことができます。
※シミュレーションはあくまで概算であり、税控除額をお約束するものではございません。実際の控除の対象・控除額については、所轄の税務署等にご相談のうえ、ご確認ください。
この制度は、すべての住宅が対象なわけではありません。令和6・7年に新築住宅に入居する場合、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準に適合する必要があります。
さらに改正建築物省エネ法が公布されたことで、将来的には原則としてすべての新築建築物に省エネ基準適合が義務化されます。これは2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減の実現に向けたもので、一般住宅も例外ではありません。
つまり、住宅ローン控除の対象外なだけでなく、そもそも省エネに適合していない新築住宅は建てることができなくなるのです。これから新築住宅の購入を検討している場合には、住宅の性能基準を確認し、省エネ基準に適合した住宅を選びましょう。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度と2年目以降で手続きが異なります。最初の年は税務署に確定申告が必要で、2年目以降は会社員のかたであれば勤務先の年末調整のみで続きが可能です。
●初年度
住宅ローン控除を初めて受ける年は、会社員のかたであっても必ずご自身で税務署に確定申告を行う必要があります。居住を開始した年は年末調整では手続きができないと覚えておいてください。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日(土日祝の場合は翌平日)に行う必要がありますが、ローンの控除の場合は1月から申告可能ですので、混んでいないうちに済ませておくことをおすすめします。
確定申告の際には、住民票の写しや住宅ローンの残高証明書、登記事項証明書、源泉徴収票、中古物件の場合は耐震基準適合証明書などの書面も必要です。書面を揃えるのに時間を要するケースもありますので早めに準備をして、確定申告に備えておくと良いでしょう。
| 必要書類 | 入手・依頼先 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 住民票の写し | 市区町村 | 自ら居住(6ヶ月以内) |
| 住宅ローンの残高証明書 | 金融機関等 | 住宅ローン残高 |
|
|
|
| 給与等の源泉徴収票等 | 職場 | 所得税額等 |
(認定長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅の場合)下記のいずれか
|
不動産会社・建築士等 | 耐震性・性能を有すること |
(中古住宅の場合)下記のいずれか
|
|
耐震性を有すること |
●2年目以降(給与所得者の場合)
2年目以降は、勤務先の年末調整で控除を受けることができますので確定申告は不要です。生命保険料控除などと同様に、住宅ローンの残高証明書を提出する必要がありますので、大切に保管してください。
住宅ローンをお持ちのかたは、毎月の返済額や返済期間を減らす効果がある繰り上げ返済を検討しているかたも少なくありません。ただ「残債を減らすと住宅ローン控除の効果が薄まるのでは?」と悩まれるかたも多いのではないでしょうか。
このお悩みは、借入金利や金利プラン(固定・変動など)によって考え方が異なります。通常、繰り上げ返済をする場合にはどれだけメリットが出るのかのシミュレーションを行いますので、その金額と繰り上げ返済により残債を減らした場合の住宅ローン控除への影響なども比較し、有利なほうを選択するのが良いでしょう。
借入金利が比較的高い場合、控除期間中であっても繰り上げ返済を行うことでメリットが出る可能性がありますが、低い金利で借入れを行なっている場合には控除期間中は繰り上げ返済をしないほうが結果的に支出を抑える可能性もあります。控除期間中はあえて繰り上げ返済を行わずに資金を貯蓄しておき、控除期間終了後に繰り上げ返済をまとめて行うかたもいらっしゃいます。
ただし変動金利で借入れを行なっている場合、将来の住宅ローン金利の予想は簡単ではありませんので、金利の上昇を考慮して選択する必要があります。
一般的には、残債が住宅ローン控除の上限を超える部分があれば繰り上げ返済は効果が見込めます。その上限を下回る部分については慎重に検討を行いましょう。
※最新情報は国土交通省のWebサイトをご確認ください。