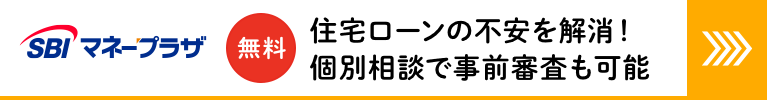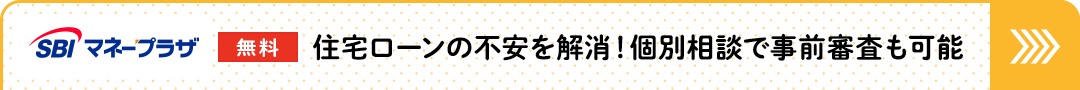5,000万円の住宅ローンの借り入れを検討しているかたの中には、「どれくらいの年収が必要になるのだろう」「自分の年収でも返済していけるのだろうか」と不安に思われるかたもいると思います。
住宅ローンの借り入れを検討する際に注意しなければならないのが、「金融機関から借りられる金額」と「無理なく返済できる金額」は異なる点です。
また、利用する住宅ローン金利や借入金額・期間によって、毎月の返済負担や総返済額も変わります。
そこで本記事では、5,000万円の住宅ローンを組む際の目安となる年収について、金融機関からの借入可能額と無理なく返済できる返済可能額の視点から解説します。
長期的に無理なく返済するためのポイントや、夫婦二人の収入で借り入れする場合の注意点なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
5,000万円の住宅ローンを組むために必要な年収について、「金融機関から借り入れできる年収」と「無理なく返済できる年収」という異なる視点から解説します。
5,000万円の借り入れをするにあたって必要な年収の目安は、700万円以上です。
これは、金融機関ごとに設定している審査金利と返済比率の上限から導き出される金額です。
審査金利とは、金融機関が審査にあたって使用する金利のことで、借入期間中の金利上昇リスクを想定し、実際に適用される金利より高めの3%~4%に設定されることが一般的です。
一方の返済比率は、住宅ローンやそのほかの返済が年収に対して占める割合を示すものです。金融機関によって異なり、公表はされていませんが一般的には30%~40%といわれています。
たとえば、年収700万円の人が、審査金利が3.5%、返済比率の上限が35%の金融機関を利用する場合、およそ4,940万円と年収の約7倍の借り入れが可能です(借入期間35年・元利均等返済で試算)。
このように、審査金利と返済比率の上限という指標を用いると、利用する金融機関によって詳細は異なりますが、年収のおよそ7倍程度が借入可能額の上限と考えられます。
結果として、金融機関から5,000万円を借り入れする場合、年収700万円以上が一つの目安となるのです。
5,000万円を借り入れ可能な年収は700万円以上が目安となりますが、無理なく返済できる借入金額という視点では、年収800万円以上が理想です。
これは、実際の返済額や返済計画に基づくと、長期間無理なく返済できる返済比率は、20%~25%だといわれているためです。
【前提条件】
借入金額:5,000万円、年1.5%(全期間固定金利)、借入期間:35年(ボーナス返済なし)、返済方法:元利均等返済
たとえば、年収800万円で返済比率を25%までに抑える場合、借入金額は5,443万円となります。
実際の適用金利や借入期間によって異なりますが、年収800万円であれば、無理のない返済比率の範囲内で5,000万円の借り入れが可能です。
住宅ローンの返済は長期間にわたるため、毎月の返済額だけでなく総返済額も考慮しながら、綿密な返済計画を立てることが重要です。
金利が上昇すると返済額も増えるため、変動金利や期間選択型の住宅ローンを利用する場合は、借入期間中の平均金利がどれくらいになるかなども試算するとよいでしょう。
ここでは、実際に5,000万円を借り入れした場合の「金利別」「借入期間別」の返済額のシミュレーションを紹介します。
適用金利別に毎月返済額と総返済額のシミュレーションをしてみました。
【前提条件】
借入金額:5,000万円、借入期間:35年、返済方法:元利均等返済、ボーナス返済なし
| 適用金利(年率) | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
| ① 1.2% | 145,851円 | 1,750,212円 | 61,257,234円 |
| ② 1.5% | 153,092円 | 1,837,104円 | 64,298,491円 |
| ③ 1.8% | 160,545円 | 1,926,540円 | 67,429,006円 |
適用金利1.2%と1.8%を比較した場合、毎月の返済額の差は、およそ15,000円(年間約18万円)ですが、総返済額でみると600万円以上の違いがあります。
総返済額の違いは家計における貯蓄残高にも影響するため、利用する住宅ローンの適用金利については慎重な判断が必要です。
なお、このシミュレーションは35年で完済する前提ですが、繰り上げ返済を利用することで、総返済額の差を少なくすることもできます。
次に、借入期間別に返済額のシミュレーションをしてみました。
【前提条件】
借入金額:5,000万円、金利:年1.5%(全期間固定金利)、返済方法:元利均等返済、ボーナス返済なし
| 借入期間 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|---|
| ① 25年 | 199,968円 | 2,399,616円 | 59,990,272円 |
| ② 30年 | 172,560円 | 2,070,720円 | 62,121,428円 |
| ③ 35年 | 153,092円 | 1,837,104円 | 64,298,491円 |
完済までの期間が短いほど、毎月・年間の返済額は増えますが、総返済額は少なくなります。
借入期間を25年と短くすると、35年の場合と比べて総返済額を400万円以上抑えられるものの、毎月の返済額はおよそ47,000円増えます。
借入期間中の家計を圧迫しすぎないように、契約時の借入期間を短くしすぎず、余裕があれば、一部繰り上げ返済するなど、無理のない返済計画を考えることが大切です。
ここでは、住宅ローン返済のポイントを3つ解説します。
住宅ローンの借入金額や返済計画を決めるうえで重要な指標である「返済比率」を計算しましょう。
返済比率は、年収に対して年間返済額(住宅ローン返済やそのほかの返済)が占める割合です。一般的に、20%~25%の返済比率が望ましいとされています。
たとえば、年収800万円で返済比率を25%までとした場合、年間の返済額は200万円(800万円×25%)となります。毎月の返済額に直すと、およそ167,000円です。
ただし、住宅ローン返済以外に車のローンや携帯電話の分割購入などの支払いがある場合、それらを含めて返済比率を計算する必要があります。
また、返済比率は、借入期間によって変わる点にも注意が必要です。借入期間が短いほど年間返済額が増え、返済比率も上がります。
つまり、同じ年収でも返済計画(借入期間)によって、住宅ローン審査や借入金額に影響する可能性があるのです。
そのため、住宅ローン以外の支出や借入期間などを考慮しながら返済比率を計算し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
長期間の返済が前提となる住宅ローン返済では、ライフイベントを踏まえながら、家計支出が増える時期などを考慮することも大切です。
人生の三大資金といわれる、「住宅資金」「教育資金」「老後資金」ですが、住宅ローン返済は、将来必要となる教育資金や老後資金に影響します。
子どもの教育費がかかる時期と期間、老後資金として必要な積立額などを把握するために、ライフプランシミュレーションを作成するのも一つの方法です。
それを基に、長期の視点で無理のない住宅ローン返済計画を立てましょう。
同じ5,000万円を借り入れするとしても、返済方法によって総返済額が変わります。総返済額を減らしたい場合、元金均等返済にする方法が考えられます。
住宅ローンの返済には、「元利均等返済」と「元金均等返済」があり、それぞれの特徴は次のとおりです。
| 元利均等返済 | 元金均等返済 |
|---|---|
| 毎月の返済額が一定になるように返済する方法。返済額が一定のため、返済計画を立てやすい。 | 元金の返済が毎月一定になるように返済する方法。返済開始当初の返済額は大きく、返済が進むにつれ、毎月の返済額が減少。 |
元利均等返済と元金均等返済でシミュレーションをすると、総返済額は次のような違いが生じます。
【前提条件】
借入金額:5,000万円、金利:年1.5%(全期間固定金利)、借入期間:35年 ボーナス返済なし
| 元利均等返済方式 | 元金均等返済方式 | |
|---|---|---|
| 総返済額 | 64,298,491円 | 63,156,108円 |
元金均等返済の総返済額は、元利均等返済に比べて110万円程度減らせます。ただし、元金が多い返済開始当初の返済額は高くなるため、問題なく返済できるかしっかりと検証することが大切です。
また、元金均等返済方式は、返済開始当初の毎月の返済額が増える分、住宅ローン審査にも影響する点や、変動金利型の住宅ローンを利用する場合は金利が上昇した場合の「5年ルール」、「125%ルール」がない点に注意しましょう。
※5年ルール:借入期間中に金利が上昇しても、5年間は毎月の返済額が変わらないというルール
※125%ルール:5年経過後に返済額が上昇する場合でも、今までの返済額の125%までしか上がらないというルール
ここでは、住宅ローンを組む際の注意点を3つ紹介します。
一般的に、変動金利の適用金利は半年ごとに見直されますので変動金利の住宅ローンを利用する場合、借入期間中に金利が上昇し、返済額が増える可能性がある点に注意が必要です。
通常、変動金利の適用金利は、各金融機関が設定する「店頭金利」と「店頭金利からの優遇幅」によって決まります。
多くの金融機関では、店頭金利は日銀の金融政策や景気動向によって変動する短期プライムレート(金融機関が優良企業に短期間で融資する場合の最優遇貸出金利)を基準に決められています。
店頭金利からの優遇幅をどれくらいに設定するかは、各金融機関の営業方針などによって異なります。
変動金利の利用を検討するのであれば、金利動向に影響を与える要因や仕組みについて、理解しておくことが大切です。
同時に、金利上昇した場合の毎月の返済額や家計への影響をシミュレーションしておくとよいでしょう。
・収入合算を想定している場合
収入合算は、住宅ローン契約者(主債務者)の収入に、パートナーや親の収入を合算して借り入れする方法です。収入合算者は、住宅ローンの連帯保証人になる必要があります。
金融機関によって合算できる収入や条件は異なりますが、審査対象となる収入が増えるため、借入金額を増やせます。
ただし、一般的に、団体信用生命保険(以下「団信」)に加入できるのは主債務者のみであり、収入合算者は対象となりません。そのため、合算者が亡くなったり、疾病などで働けなくなったりした場合でも保険金は下りず、住宅ローン返済は続きます。
なかには、収入合算で夫婦二人とも団信に加入できる商品もありますが、夫婦どちらかの収入がなくなる、あるいは減ることも想定して利用する必要があります。
・ペアローンで申し込む場合
ペアローンは、一つの借り入れに対し、パートナーそれぞれが住宅ローン契約者となりローンを組む方法です。
たとえば、夫が3,000万円のローン、妻が2,000万円のローンを組み、それぞれがお互いの連帯保証人となります。
ペアローンは、それぞれが独立した住宅ローン契約であるため、団信のほか住宅ローン控除もそれぞれ受けられる点がメリットです。
ただし、住宅ローン返済中に子どもの出産や育児等のため、収入が減ることも考えられます。こうした状況において、家計に対する住宅ローン返済の負担が重くなり過ぎると、返済継続が困難となるリスクもあります。
ライフプランや働き方をしっかりと考える、または自己資金や頭金をできるだけ準備するなどの対策を取ることが大切です。
住宅購入後にかかる固定資産税や火災保険料、マンションであれば管理費や修繕積立金などの住宅ローン以外の支出も考慮しておくことが重要です。
月々の住宅ローン返済だけでなく、購入後の維持費を含めた出費が、収入に対してどれくらいを占めるかを試算し、確認しておくと安心です。
また、マイホームの購入時には、物件の購入代金以外に、不動産会社に支払う仲介手数料や印紙税、住宅ローン事務手数料、登記費用などの諸費用が必要です。
物件購入に対してかかる諸費用を合算して必要資金を算出し、それも考慮に加えて適切な借入金額と返済計画を立てましょう。
住宅ローンを5,000万円借り入れするために必要な年収の目安は、700万~800万円です。
ただし、利用する住宅ローンの適用金利や借入期間に応じて、毎月の返済負担は変わります。
また、長期間にわたる住宅ローン返済では、家計の状況の変化や金利上昇の可能性も考えられます。特に、収入合算やペアローンで借り入れする場合は、パートナーの収入の変化や病気などのリスクを考えることが重要です。
さらに、マイホーム購入後の税金や保険料、修繕費の積み立てなどの維持費も含めて、現実的な借入金額と返済プランを考える必要があります。
SBIマネープラザでは、住宅ローン商品の選び方や返済プラン、団信など、住宅ローン全般についてご相談いただくことが可能です。
収入や借入希望金額に合わせたシミュレーションを基に、最適な住宅ローン商品をご提案させていただきます。
専任の担当者と店頭でのご相談のほか、オンラインや電話での相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。
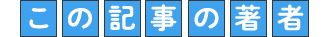

株式会社あつみ事務所 代表
建設会社・ハウスメーカーで建築設計、不動産売買仲介を経て、不動産・住宅専業ライターとしても活動。これまで不動産・金融メディアを中心に300本以上の記事執筆を手掛ける。現在、不動産売買や住み替えを中立的な立場でサポートするサービスを提供しながら情報発信を行う。
【保有資格】宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級技能士・住宅ローンアドバイザー